前回の記事では、弁護士・税理士・社労士・司法書士・行政書士など、いわゆる「士業」の先生方にとって、ホームページのSEO対策は非常に有効であるというお話をしました。
前回の記事はこちら
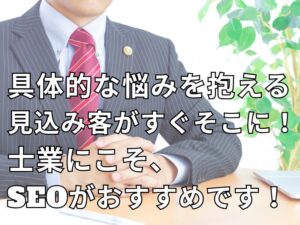
けれども、ホームページのSEO対策を始めても、思うように問い合わせが増えない場合があります。
その原因の多くは、基本戦略や信頼性、導線設計の不備です。
特に高単価案件を扱う士業では、検索からの問い合わせは非常に価値があります。
適切に運用できれば、少ないアクセスでも高単価案件の獲得につながります。
しかし、戦略を間違えるとアクセスは増えても問い合わせがほとんど発生せず、時間とリソースを無駄にしてしまうこともあります。
今回は、士業の方でSEOで失敗する人の共通パターンと改善策についてお伝えしていきます。
1・士業SEOで失敗する人の共通パターンと改善策

① 専門性が曖昧
「何でもできます」は、誰の心にも響きません。
専門分野を絞り込めないと、競合が多い中でサイトの差別化が難しく、検索順位もなかなか上がりません。
「あなたの悩みは、この専門家に相談すれば解決できる」とユーザーに思ってもらうことが、Web集客の第一歩です。
【改善策】
まずは、1〜2分野に絞って専門性を明確に打ち出しましょう。
特定の分野に特化することで、「この人はこの分野のプロだ」という信頼感が生まれ、ユーザーの「刺さる」記事を作成できるようになります。
専門性が明確になれば、サイト全体の評価も上がり、結果として検索順位も向上していきます。
② 1記事に検索意図を詰め込みすぎ
あれもこれもと情報を詰め込みすぎると、記事のテーマが曖昧になり、検索エンジンからもユーザーからも評価されにくくなります。
「この記事は何について書かれているの?」
「知りたい情報がどこにあるか分からない…」
このように読みにくさを感じさせると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。
【改善策】
「1記事=1質問」のルールでコンテンツを分割しましょう。
例えば、「離婚の相談」という大きなテーマを扱う場合でも、「離婚の慰謝料相場」「離婚時の財産分与」「親権の決め方」など、具体的な一つの疑問に絞って記事を作成します。
それぞれの記事を内部リンクで丁寧につなげていくことで、サイト全体の専門性が高まり、Googleも「このサイトは、離婚に関するあらゆる疑問に答えてくれる専門的なサイトだ」と評価してくれるようになります。

③ 更新が止まる、または不定期で数が少ない
記事を一時的に頑張って書いた後、放置してしまうと、せっかく上がった検索順位は徐々に下がっていきます。
情報が古くなるとGoogleの評価も下がり、ユーザーからの信頼も失われてしまうからです。
また、「手が空いたら」という不定期な更新ペースでは、なかなか検索順位を上げることはできません。
【改善策】
まずは「月2〜4本」と目標を決め、更新ペースを守り続けましょう。
継続的な情報発信は、Googleに「このサイトは常に最新で質の高い情報を提供している」と評価される重要なポイントです。
ある程度記事が溜まってきたら、新規記事の作成だけでなく、既存記事の追記や改訂も忘れずに行いましょう。
継続は力なり。地道な努力こそが、安定した集客へと繋がります。

④ 相談事例を出さない
相談事例を出さないのは、お客様が抱える悩みを理解していないと判断されてしまう、致命的な失敗です。
検索ユーザーが一番知りたいのは、「自分と同じような悩みを持つ人がどうやって解決できたのか」という具体的な成功事例です。
その情報を出し惜しみしてしまうと、「この事務所は信頼できない」と思われ、問い合わせには繋がりません。
【改善策】
匿名化した実務事例を公開し、安心感と専門性をアピールしましょう。
「事例を出すと、自分で解決されてしまうのでは?」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。
資格や専門知識がない方がインターネットの情報だけで解決するのは困難です。
むしろ、「自分と似たケースだ!」と感じたお客様が、安心して相談を依頼してくれるようになります。

⑤ 料金や対応範囲が不明瞭
料金やサービス内容が明確でないと、ユーザーは「いくらかかるんだろう?」「自分の悩みに対応してくれるかな?」と不安になり、すぐにサイトを離れてしまいます。
せっかく興味を持ってくれた見込み客を逃してしまう、もったいない失敗です。
【改善策】
料金レンジやモデルケースをサイトに明記しましょう。
例えば、「〇〇円〜」という料金の目安を提示したり、「相談料は30分〇〇円」のように初期費用を明確にすると、ユーザーは安心して問い合わせることができます。
さらに、「遺言書作成サポートの場合:〇〇円〜」といった具体的なモデルケースを示すことで、より明確なイメージを持ってもらえます。
料金をオープンにすることで信頼感が高まり、「自分でも依頼できるかも」と感じた見込み客からの問い合わせが増えていきます。
⑥ CTA(問い合わせ導線)が弱い
せっかくブログ記事を読んでもらっても、問い合わせへの導線が明確でないと、ユーザーは「次は何をすればいいんだろう?」と迷ってしまいます。
記事を読み終えて満足し、そのままサイトを離れてしまうのは、非常にもったいない失敗です。
【改善策】
初回相談、無料診断、資料ダウンロードなどのボタンを、記事の途中と最後に設置しましょう。
ユーザーが「もっと知りたい」「相談したい」と感じた瞬間に、すぐ行動できるボタンを用意しておくことが重要です。
CTA(Call To Action)を複数設置することで、ユーザーの興味関心に合わせた行動を促すことができます。
記事の内容に合わせて、例えば「〇〇でお悩みの方はこちら」のように具体的な文言を加えると、さらに効果が高まります。

⑦ ローカルSEO対策が不足
地域に根ざしたビジネスである士業にとって、ローカルSEO対策を怠るのは大きな機会損失です。
「地域名+専門分野」で検索する見込み客を取りこぼしてしまうからです。
せっかく質の高いサイトを運営していても、お客様があなたの事務所を見つけられなければ意味がありません。
【改善策】
Googleビジネスプロフィールを最適化し、地域検索での露出を強化しましょう。
具体的な対策は以下の通りです。
- Googleビジネスプロフィールの登録・最適化
事務所の住所、電話番号、営業時間などを正確に記載しましょう。 - 写真の充実
事務所の外観や内観、スタッフの顔写真を掲載することで、お客様は安心して訪問できます。 - 口コミへの対応
寄せられた口コミには丁寧に返信し、信頼感を高めましょう。返信文章をコピペで使い回すのは厳禁です。 - 最新情報の投稿
ブログ記事やセミナー情報など、最新の情報を定期的に投稿することで、Googleからの評価も向上します。
ローカルSEO対策を強化すれば、地域でサービスを探しているお客様にあなたの事務所を効果的にアピールできます。
⑧ YMYL対策が弱い
士業のサイトは、人生を左右する重要な情報(YMYL: Your Money or Your Life)を扱っているため、Googleから非常に厳格な評価を受けます。
専門性や信頼性が伝わらないと、Googleからの評価は低くなり、検索上位に表示されません。
どれだけ素晴らしい記事を書いても、誰が書いたか不明なサイトは信頼されず、集客にはつながりません。
【改善策】
「この情報は信頼できる」とユーザーに感じてもらうために、専門性を明確にアピールしましょう。
具体的な対策は以下の通りです。
- 執筆者・監修者の明記
記事には必ず執筆者の氏名と、必要であれば監修者の情報を記載してください。 - 資格・経歴の掲載
資格やこれまでの経歴を詳しく掲載し、なぜその分野の専門家であるかを明確に示しましょう。 - 顔写真の公開
執筆者や事務所代表の顔写真を掲載することで、サイトに人間的な信頼感が生まれます。 - 権威性のある情報の引用
官公庁や公的機関の情報を引用する際は、出典元を明記しましょう。
これらの対策を徹底することで、サイトの信頼性は大きく向上し、Googleからの評価も上がります。

⑨ 低品質コンテンツを丸投げ
コンテンツ作成を外注する際に、すべてを丸投げしてしまうと、差別化できない低品質な記事ができあがってしまいます。
テンプレート通りの内容や、誰にでも書ける一般的な情報だけでは、検索エンジンにもユーザーにも評価されません。
結果として、他の多くのサイトに埋もれてしまい、集客につながるどころか、時間と費用だけが無駄になってしまいます。
【改善策】
事務所が持つ専門的な「一次情報」を提供し、コンテンツの質を高めましょう。
記事の骨子や専門的な知見は事務所の先生が提供し、その情報をWebマーケティングのプロが読みやすい文章に編集・執筆するという分業体制を構築してください。
- 骨子・一次情報
事務所が「どんなユーザーに、何を伝えたいか」という目的を明確にし、専門家ならではの知識や実務経験を盛り込みます。 - 編集・執筆
SEOの知識を持つ編集者が、その一次情報を基に、読者の検索意図に沿った分かりやすい記事に仕上げます。
この方法なら、専門家ならではの独自性を保ちつつ、SEOにも強い高品質なコンテンツを効率的に作成できます。
⑩ ページ速度やモバイル体験が悪い
ページの読み込みが遅かったり、スマートフォンで表示が崩れたりすると、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。これは検索エンジンの評価を下げるだけでなく、せっかく集めた見込み客を逃す大きな原因となります。
Googleは、ユーザーにとって快適なサイトを高く評価するため、ページ速度やモバイル対応は検索順位に直結する重要な要素です。
【改善策】
サイトの表示速度を改善し、モバイルフレンドリーな体験を提供しましょう。
具体的な対策は以下の通りです。
- 画像の最適化
画像を圧縮したり、次世代フォーマット(WebPなど)に変換したりすることで、ファイルサイズを小さくします。 - 遅延読み込み(Lazy Load)の導入
画面に表示されるまで画像や動画の読み込みを遅らせることで、初期表示速度を向上させます。 - 不要なスクリプトの削除
使っていないプラグインやJavaScriptのコードを削除し、サイトを軽くしましょう。 - モバイル対応
スマートフォンやタブレットでも見やすく、操作しやすいデザインを徹底します。
これらの対策を行うことで、ユーザーがストレスなくサイトを閲覧できるようになり、検索順位とコンバージョン率の両方を改善できます。

⑪ 計測をしていない
Webサイトを公開しただけで満足していませんか?
どの記事がどれくらい読まれているのか、どんなキーワードで訪問しているのかを把握しないと、改善のしようがありません。
データに基づかない集客は、地図を持たずに旅に出るようなものです。
闇雲に記事を増やしても、時間と労力だけが無駄になってしまいます。
【改善策】
Googleアナリティクスとサーチコンソールを導入して、サイトの状況を「見える化」しましょう。
これらの無料ツールを使えば、以下のことがわかります。
- どの記事が人気か
読まれている記事がわかれば、そのテーマをさらに深掘りしたり、関連する記事を作成したりできます。 - どんなキーワードで検索されているか
ユーザーの検索意図が明確になり、よりニーズに合った記事を作成できます。 - どこから訪問しているか
SNSや他のサイトなど、流入経路がわかれば、集客戦略を立てやすくなります。
これらのデータを基にKPI(重要業績評価指標)を設定して改善を繰り返すことで、効果的に集客力を高めていけます。
⑫ 法令や表記が不十分
ウェブサイトにプライバシーポリシーや運営者情報がないと、ユーザーは「このサイトは信用できるのだろうか」と不安に感じ、離脱してしまいます。
また、法令に準拠していないと、法的リスクを抱えることにもなりかねません。
士業サイトは特に、高度な専門性と信頼性が求められます。
基本的な法的表記が不足しているだけで、その信頼性は大きく損なわれてしまいます。
【改善策】
サイトの信頼性を高め、法的リスクを回避するために、必要な表記を徹底的に整備しましょう。
最低限、以下の情報を明確に掲載してください。
- プライバシーポリシー
ユーザーから取得した個人情報をどのように扱うかを明記します。 - 免責事項
提供する情報の正確性や完全性を保証するものではないことを記載し、万が一のトラブルに備えます。 - 運営者情報
事務所名、代表者名、連絡先、所属士業会の登録番号などを記載し、サイトの運営元を明らかにします。
これらの表記は、ユーザーに安心感を与えるだけでなく、プロフェッショナルとしての誠実さを示す重要な要素です。
2・失敗を避けて成果を出すポイント

SEOで成功し、問い合わせを増やすには、ただ記事を増やすだけでは不十分です。
以下の5つのポイントを徹底することで、集客の質が劇的に向上します。
- 専門性を明確にし、ユーザーの意図に沿った記事を作る
「何でも屋」ではなく「この分野のプロ」だと認識してもらいましょう。 - 相談事例や定量データで信頼性を示す
具体的な実績を提示することで、あなたのサービスがどのように役立つかをユーザーに伝えます。 - 内部リンクやCTAで問い合わせ導線を最適化する
記事を読んだユーザーが、迷うことなく問い合わせにたどり着けるように、丁寧な導線を作りましょう。 - 継続的にサイトを更新し、情報を常に最新に保つ
Googleは常に新しい情報を評価します。
地道な更新が信頼と安定した順位に繋がります。 - ページ速度やモバイル対応など、技術面も改善する
ユーザーがストレスなくサイトを閲覧できるよう、快適な環境を整えましょう。
これらを徹底すれば、アクセス数が少なくても質の高い問い合わせが発生しやすくなり、高単価の案件を安定的に獲得できます。
3・今すぐできるアクション

web集客の失敗を避け、問い合わせを増やすために、まずはあなたのサイトが上記の12項目に当てはまっていないかチェックしてみましょう。
今日からできる具体的なアクションを3つご紹介します。
- 専門分野を絞り込み、既存記事のテーマを整理する
- 匿名化した相談事例や、事務所の実績データを公開する
- すべての記事に問い合わせや無料相談へのCTAボタンを設置する
無料SEO相談・ライティングサポートも提供しています。

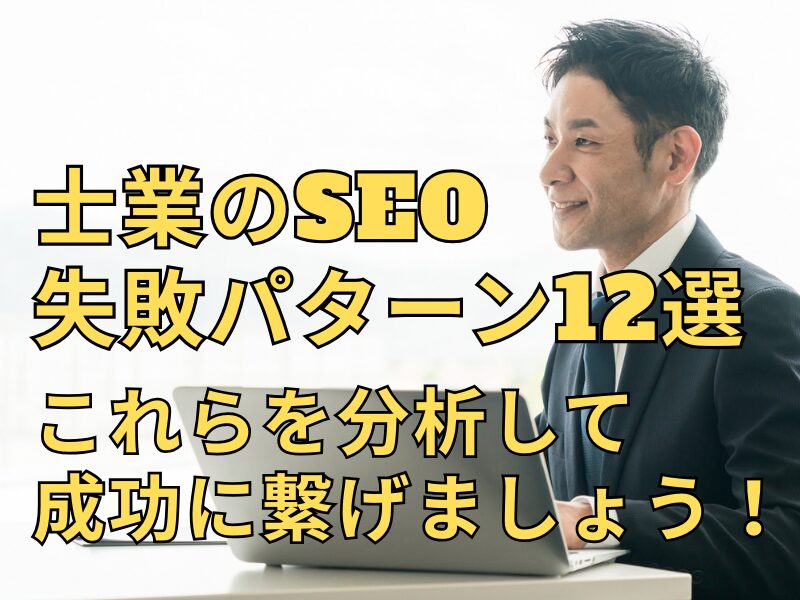
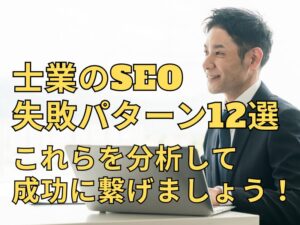

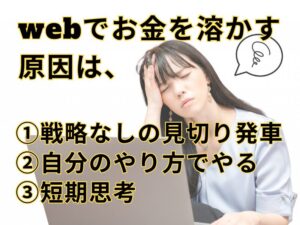
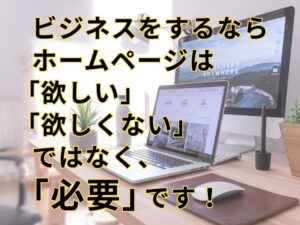
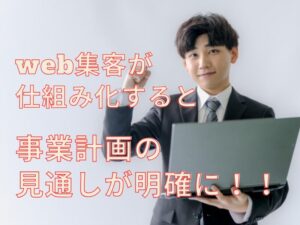

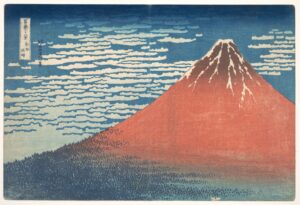


コメント